7月初旬、東京国立博物館で始まったばかりの「古代ギリシャ展」と東京都美術館で開催中の「ポンピドゥー・センター傑作展」で、第三回目の研修を行いました。

まずは「古代ギリシャー時空を越えた旅」。
古代ギリシャ美術については、みな1年生の必修授業「西洋美術史概説1」で習っているけれど、どれだけ覚えていたかな?
まずは入館前に事前レポートで学習してきたことを確認。
古代ギリシャの壺絵の代表的な様式である黒像式と赤像式の違い。褐色系の地に人物像が黒く描かれているのが黒像式、逆に黒地に人物が赤く浮き出しているのが赤像式。
それから古代ギリシャの人体表現についても確認しておきます。
今回の展覧会は全点、ギリシャの美術館から出展です。
いわゆる大作はないけれど、。紀元前7000年に始まるエーゲ海文明から紀元前1世紀のヘレニズム、古代ローマにおけるギリシャ文化の影響までという約7000年に及ぶ流れが、多種多様な作品により丁寧に追われていましたね。
最後のセクションはちょうど春に行った「ポンペイの壁画展」でギリシャ文化の影響を受けた神話主題の壁画など見てきたところなので、つながったのではないでしょうか?
午前の紀元前の7000年間に次いで、午後は一気に時代をくだり、20世紀の70年間を扱った展覧会「ポンピドゥー・センター傑作展」へ。
事前学習でポンピドゥー・センターそのものについての発表。
1977年に開館した同センターは世界有数の近現代美術コレクションを誇る美術館であるだけでなく、美術や音楽、ダンス、映画など、さまざまな芸術の拠点でもあります。
設計はイタリア人建築家レンゾ・ピアノとイギリス人建築家リチャード・ロジャースが手がけ、配管や階段、エスカレーターなどが外観と内部に剥き出しになった前衛的な建物として、パリの石造りの旧市街のなかで異彩を放っています。
名前は前衛美術に造詣が深く、計画を後押しした当時の大統領ポンピドゥーの名前をとっています。
ちなみにこの子たち「リサとガスパール」のリサの住まいでもあるのです。
ポンピドゥー・センターについて学んだ後は、20世紀美術のいくつかの運動についても確認しておきます。印象派以降の近現代美術ハ、次々と色々な動きが出てくるのが特徴。
オルフィスムってなんだろう? アンフォルメルって聞いたことがあるかな?
オルフィスムはキュビスムから生まれたけれど、キュビスムの代表格ピカソやブラックの作品には見られない色を使っているのが特徴。今回はその代表的な作家ドローネーの代表作「エッフェル塔」が来ていました。
フランス語で「非定型」を意味するアンフォルメルは、第二次大戦後、ヨーロッパで生まれた芸術運動。形が失われるほど抽象化を進めた作品などが作られ、時代背景もあり、形を失った人体表現が見られます。表現主義的な表現があることから、幾何学的でクールな抽象絵画に対して、「熱い抽象」とも呼ばれました。
今回の「傑作展」は、1906年からセンターが開いた77年までの近代美術の流れを、フランスで活躍した芸術家を中心に、1年1作家1作品という構成で辿るという、とてもユニークな企画展。
そのため展示デザインも、パリを拠点に活躍し、各国の美術館建築を手がけたこともある建築家・田根剛氏が担当し、意欲的な試みがされていました。
各セクションはフランスの三色旗(赤・青・白)に基づいて壁の色が変えられ、時代の雰囲気が伝えると同時に、作品を引き立てる色の選択がされていました。
また最初の2フロアは壁がジグザグに設置されることで作品の傍にある作家のポートレートや言葉とともに一作ずつ向き合えるようになっていたり、最後の真っ白なフロアは中央に置かれた輪の形の台に作家の言葉、その台と対面する壁にその作品が展示され、部屋の真ん中から言葉と作品を同時にとらえられるようになっていましたね。
1945年、第二次大戦の終わった年が絵画でも彫刻でもなく、その年に発表されたエディット・ピアフのラヴィアンローズ(バラ色の人生)というのも、その前年が解放されたパリで抱擁する恋人たちを写したゼーベルガーによる写真、その次の年がアンリ・ヴァランシによる音楽を視覚化した薄いバラ色の作品というのも、考え抜かれたセレクションの展覧会でした。
さて、次回は最終回。どんな作品と出会えるでしょうか?













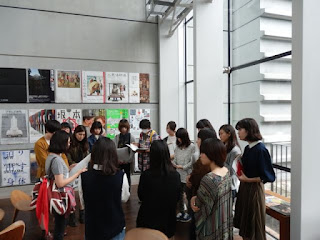

 アールヌーヴォーのガラス工芸家は日本でも人気が高く、今回の展覧会もサントリー美術館所蔵作を中心に構成されていました。
アールヌーヴォーのガラス工芸家は日本でも人気が高く、今回の展覧会もサントリー美術館所蔵作を中心に構成されていました。












