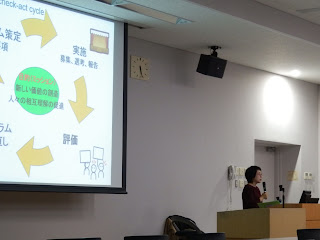ホルベイン画材株式会社は、ルネサンス時代のドイツの画家にちなんで命名された、洋画材料専門の老舗です。
油絵具や水彩絵具をはじめ、さまざまな画材を扱っています。
油絵具や水彩絵具をはじめ、さまざまな画材を扱っています。
画材の販売以外にもアーティストとのコラボやワークショップ、また若いアーティストの育成なども手掛けています。
野尻さんが室長をなさっている商品企画室の活動は、商品開発というよりも、顧客への間口を広げていくことだそうです。

今日、描画の方法もデジタル化が進むなか、画家を含め、絵具やキャンヴァスといった画材を使って絵を描く人達や画材職人の高齢化と減少、後継者不足、また初等・中等教育における美術授業時間の削減などにより、絵画人口が減少している現状があります。
そこで、商品企画室では、新たな切り口から、幅広い層の人達に美術に親しんでもらおうと多様な企画を立ち上げています。
たとえば、画期的な発想から生まれた、石膏像のアイドルユニット「石膏ボーイズ」。ザリガニワークス、KADOKAWAとの共同企画によるもので、2015年度に結成され、昨2016年にはアニメ化もされました。
 |
| 本学の「石膏ボーイズ」(?)も授業に参加しました。 |
昨年秋、本学では展覧会「石膏像を見に行こう!」を開催しました。その際に、現代における古典彫刻の受容として「石膏ボーイズ」を紹介し、ホルベイン画材株式会社にご協力いただきました。
野尻先生、幅広い内容のご講義をどうもありがとうございました。